もし、自分が人生の中で読んだ本の内容をすべて覚えていたとしたら、どうしますか?
教科書も単語集も地図帳の内容をすべて記憶できたとしたら、きっとテストではすばらしい点数が取れますよね。
それ以外にも、過去に読んだ新聞記事や小説、歴史本などの内容を覚えていられるとしたら、きっと生活の中でとても役に立つことでしょう。
まさに歩く百科事典みたいな存在になれるかもしれません。
ですが悲しいことに、私たちはとても心に響いた本があったとしても、どんどんその内容は忘れてしまいます。
新しい本で情報がアップデートされて古い本の記憶を忘れるのであればまだいいのです。
ところがリブラの場合、その新しい本の内容ですらも、読んだ側からどんどん忘れていきます。
これを少しでも記憶に留めておく方法はないのでしょうか?
私たちは本当に、本の内容を忘れ続けることしかできないのでしょうか?
そんなことが知りたくて、今回は樺沢紫苑さんが書いた「読んだら忘れない読書術」を読んでみることにしました。
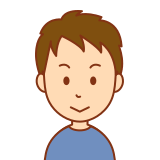
樺沢さんの本を読むのはこれで2冊目だよ!
「読んだら忘れない読書術」とは?
まさにリブラが手に入れたいと思っている能力が、この「読んだら忘れない読書術」です。
私のKindle本棚を見ると、過去に読んだ本が並んでいるのですが、タイトルと表紙の画像を見てもどんな内容だったのか、ほとんど思い出すことができません。
どうしてその本を購入したか、誰に進められてその本を読んだかはおぼろげに思い出すことができるのですが、その本に何か書いてあったのか、肝心の記憶を引き出すことができません。
タイトル:読んだら忘れない読書術
著者:樺沢 紫苑(かばさわ しおん)
出版社:サンマーク出版
発売日:2015年4月10日
樺沢紫苑さんは、精神科医であり、多数の著書を出版している作家でもあります。
それ以外にもYouTube配信、講演会、メルマガ発行・・・各方面で活躍している多才な方です。
本書では、具体的な読書術の他にも、なぜ読書が必要なのか、どんな本を選べばいいのかといった点についても、精神科医としての知見も交えながら説明してくれています。
樺沢さん自身は、月20〜30冊の読書を30年以上欠かさず続けているそうです。
シンプルに計算しても、1日に1冊程度は読了するというペースですよね。
毎日多忙な日々を過ごしているはずなのに、内容を覚えておくことに加えて、どうやってそれだけの読書時間を確保しているのでしょうか?
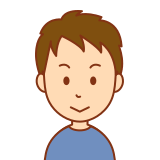
これは忙しい社会人にも応用できる、読書時間の作り方が学べそう!
樺沢さんの「神・時間術」についてはこちら。
ポイント1:10年経っても忘れない〜「記憶に残る読書術」
本書では、本を読んでから「1週間に3回アウトプットする」と記憶に残ると書かれています。
これは脳科学にも裏付けられた記憶の法則で、何度も使用された情報は脳で「重要な情報」と認識されるため、長期的に保存されるそうです。
樺沢さんの場合は、本を読みながらメモを取る、本の内容を人に話す、本の感想をSNSでシェアする、書評を書く行為をアウトプットとしているとのことでした。
これらを1週間以内に3つ行うことで、やらないときと比べて圧倒的に記憶に残ると書かれています。
さて、リブラはこれをどのように応用できるでしょう?
私の場合、基本的に本はKindleで読むようにしているので、マーカーでラインを引くことは簡単にできそうです。
今まではなんとなく「本はキレイな状態で保存しなければならない」という固定概念に縛られていましたが、Kindleのマーカーであれば簡単に削除もできるので、少しずつ試してみましょうか。
また書評を書くというのも、現在ブログで書いているレビューをアウトプットとできるので、これもなんとかクリアできそう。
あとはレビューを1週間以内に作成できるかですね。
残りの1つのアウトプットは何ができるだろう・・・。
リアルな人間関係で自分が読んでいる本について話すことはあまりないし、SNSもやっていないし。
ですが、ブログの派生としてSNSを始めることには興味を持っているので、Xで現在読んでいる本について共有するのもいいかもしれないですね。
3つ目のアウトプットは、今後のリストに加えておこうと思います。
<アクションプラン>
本を読んでから1週間以内に3回のアウトプットを行う。
ポイント2:効率的に読書をする〜「スキマ時間読書術」
みなさん、ご自身の読書時間は十分確保できていると思いますか?
私も含めて「読書はしたいけれどその時間がない」というのが現状ではないでしょうか?
樺沢さんはそれを、読書ができない人に最も多い「言い訳」とバッサリ言い切っています。
なんとも耳が痛い!
実際に彼は、月30冊の読書を、全てスキマ時間だけでこなしているそうです。
「そんなに本が読めるんだったら、もしかして樺沢さんの一日はスキマだらけなのでは?」
などということはありません。
人によってスキマ時間の定義は異なるかもしれませんが、樺沢さんの場合は「移動時間」に読書を行なっているとのことです。
リブラを含めた一般的なサラリーマンにとって、一般的なスキマ時間の代表としては、やはり通勤時間ではないでしょうか?
私の場合は、片道で約1時間半の通勤時間なので、平日は1日に3時間の「移動時間」があります。
この中で30分程度は歩いているので本を開く時間には充てられないと考えても、残りの2時間半は読書タイムとして使うことができますね。
通勤電車の中で周りを見回すと、どんなことをしている人が多いでしょうか?
始業に向けて休息を取る人、SNSをチェックする人、ゲームでリフレッシュする人、動画を見る人など、移動時間の過ごし方は人それぞれです。
私の場合は何をして過ごしていることが多いでしょうか?
ネットスーパーの注文、好きなブログのチェック、ラジオビジネス英語を聞くなど、大体はスマホを触って何かしていますね。
それに加えて、Apple Musicで音楽を聴いていたりすることも多いです。
ですが、意識的にそれを読書タイムにしていたかと言われると、そうでもなかったかもしれません。
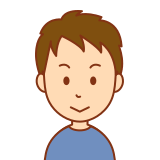
正直にいうと書籍代をケチって、あんまり本は買ってなかった!
これからは読書予算を立てて、自分の糧になるような本は買ってもいいというルールにするのがいいかもしれません。
<アクションプラン>
通勤時間を読書時間に変化させる。
ポイント3:「速読」より「深読」を意識する〜「深読読書術」
樺沢さんは一ヶ月に30冊の本を読みますが、たくさんの本を早く読むことを進めているわけではありません。
むしろペースは遅くてもいいので、本を「議論できる水準」で読み込むことを推奨しています。
ここはリブラもすごく共感するポイントです。
ときどきBizmatesのトレーナーに自分が読んだ本について話すことがあります。
そんなときに「どんな本だった?どんなところが学びになった?」と聞かれても、「なんかうまく言えないけどおもしろかった!」という小学生レベルの回答しかできず、自分にがっかりすることが多いです。
その本にはどんな役立つ考え方や情報が書かれていたのか、それに対する自分の気づきはなんだったのか、本を読んでいる最中は明確だったとしても、その内容はすぐに忘れてしまうことが多いですよね。
だからこそ、樺沢さんはメモを取ることをアウトプットとして推奨しているのだと思います。
それが質の高い読書につながるのですね。
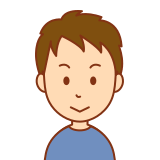
これを書きながら、アウトプットの3つ目は「Bizmatesのトレーナーに読んだ本について話す」ができるじゃんと気づいたよ!
<アクションプラン>
内容についてトレーナーとディスカッションしたり、レビュー記事を書くことを前提にして、本を読み込む。
まとめ
あとがきに書かれていたのですが、そもそも精神科医である樺沢さんが、なぜ読書術の本を出版したのでしょう?
そこには、患者さんとのこんなエピソードが書かれていました。
病気になった患者さんに病気についてわかりやすく書かれた小冊子を渡しても、患者さんは読みません。そこには病気を治すために患者さんがすべきこと、できることが全て書かれていますから、それを読んで実行していただければ、病気を治すのに大いに役立つはずなのですが、そうした本を読まないのも、普段から本を読む習慣がないからです。
これは悲しい現実ですね。
だからこそ、樺沢さんは本書を出版した理由を下記の通り書いています。
したがって、病気にならない知識、病気の予防につながる知識、病気を治す方法を1人でも多くの人に知っていただくためには、読書を習慣にする人を増やし、日本人の読書量を増やすしかないのです。
なんとも思いやりにあふれた、熱いメッセージですね。
医師としての患者さんとの向き合い方と、読書がこんな形で繋がったのでした。
病気と戦っている患者さんにとっては、役に立つとはわかっていても、本と向き合う気力がない方もいるかもしれません。
そんなとき、私たちは周りにいる友人や家族として、患者さんの代わりに本を読むことで、治療に役立つ知識を身につけることができません。
自分が本を読むことで、身近な人を守れるかもしれない。
今後本を読む上で、重要なモチベーションをもらいました。
Thank you for reading!



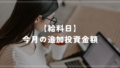
コメント