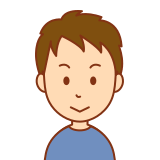
みなさん、自分が読んだ本の内容っていつまで覚えていますか?
「本を読むのは好きなんだけど、すぐに内容を忘れちゃって、知識として活用できない・・・」という方も多いのではないでしょうか?
大丈夫です。何を隠そう、リブラもその一人。
幼少期の絵本や児童文学に始まり、小説、エッセイ、専門書などたくさんの本を読んできたはずなのですが、よくも悪くも内容をすっかり忘れてしまいます。
そして、同じ本のはずなのに、なぜか毎回新鮮な気持ちで読む、という繰り返しです。
母親には「同じ本を繰り返し読んでいてよく飽きないね」とあきれられる始末。
なんとも安上がりな読書習慣ですね。
でも最近読んだ本に、読んだ本を忘れてしまう理由が「本を読んでもアウトプットをしないから」と書いてあり、これはまさに私のことだ!と思いました。
知識のアウトプットと聞くと、ちょっとおおげさな感じがして、自分が得た知識を自慢げに他人に聞かせるような絵面を想像しませんか?
ですが、この場合のアウトプットは、それに限ったものではありません。
自分が学んだ知識をリアルな知り合いに話すだけではなく、ブログでみなさんに共有するのでもいいのです!
そのため今回は、先日読み終わったばかりの「ファクトフルネス」について、アウトプットとしてのブックレビューをお届けします!
「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」とは?
数年前に流行した「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」という本をご存知ですか?
すごく話題になった本なので、すでにお読みの方も多いのではないかと思います。
タイトル: FACTFULNESS(ファクトフルネス)
著者: ハンス・ロスリング
出版社: 日経BP社
発売日: 2018年4月3日
発売当初に書店で手に取ったときからずっと気になっており、数年間にわたって読みたい本リストに入れたまま、時間が経っていました。
この本は、スウェーデン出身の医師、公衆衛生学の教授、そして剣飲み芸人(!)であるハンス・ロスリングが書いた本です。
私たちが自国以外の国に対して抱きがちなバイアスを、事実に基づいたデータで更新していくことで世界を正しく認知しよう、ということが書かれています。
とても学びが多い本なのですが、今回はその中から、特に私の心に刺さったポイントを2つご紹介します!
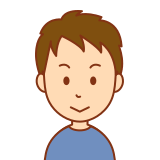
もう本のイントロダクションからレントゲン付きの剣飲み芸人のエピソードが登場するので、興味そそられまくりだよ。
ポイント1:「世界は分断されている」という思い込み
世界の国々について考えるとき、私たちはつい世界を「先進国」と「途上国」の2種類に分けて考えてしまいがちではないでしょうか。
日本に住んでいる人であれば、「先進国の一つに住んでいる私たち」と「途上国に住んでいるあの人たち」と見方をすることです。
ですが「途上国」としてひとまとめにされている国の中でも、急速に経済成長を遂げ、教育や医療の水準が劇的に改善している国は少なくありません。
つまり、世界は「あっち側」と「こっち側」の2つに分断されているというのはただの思い込みなのです。
実際には、世界の多くの人々は、貧困層でも富裕層でもない中間層に属しており、その現実を正しく認識することが大切だと、本書では書かれています。
「世界は分断されている」という思い込み
<解決策>
大半の人がどこにいるかを探して、正しく認識する
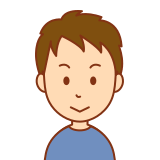
本の中では、世界を4つのレベルに分けて生活水準を比較していたよ。
ポイント2:「世界はどんどん悪くなっている」という思い込み
みなさんは学校の教科書や、上の世代の人から、世界に恵まれない人たちが多くいて、恵まれた環境にいる私たちは、彼らを助けてあげなければいけないと言われたことがありませんか?
またニュースやメディアでも、戦争や飢餓などの悲惨な場面は多く報道されますが、それが解消されたというニュースは、案外目にする機会がないのではないでしょうか。
これらの問題は、ある日突然スイッチが切り替わるように改善されるものではなく、徐々に時間をかけて、少しずつ変わっていくものなので、気づきにくいですよね。
ですが、著者はこれもデータを引用することで、世界の状況は確実によくなっていることを示しています。
本書で「減り続けている16の悪いこと」として紹介されている中では、例えばHIV感染(100万人あたりのHIV感染者数)は、1996年の549人をピークに、2016年では241人と右肩下がりのグラフを描いています。
また乳幼児の死亡率は(5歳までに亡くなる子供の割合)は、1800年には44%だったのに対して、2016年にはたったの4%です。
もちろん命を落としてしまった4%の赤ちゃんも救われるべき生命ですが、40%の赤ちゃんは乳幼児期を生き延びることができています。
対照的に「増え続けている16の良いこと」として紹介されているのは、例えば女子教育(初等教育を受ける年齢の女子のうち、実際に学校に通うこの割合)は、1970年には65%だったのに対して、2015年には90%になっています。
90%の子供たちが学校に通い、自立するための勉強をできているというのは、すばらしいことですよね。
「世界はどんどん悪くなっている」という思い込み
<解決策>
悪いニュースの方が広まりやすいと覚えておこう
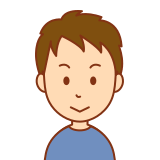
リブラも自分から勉強するようになって、やっとわかった学校教育のありがたみ。
まとめ
本記事では、2つの思い込みにフォーカスしてレビューを書きましたが、本書内では全部で10個の思い込みが紹介されています。
そして思い込みを捨ててファクトフルネスを実行するための大まかなルールが記載されています(この記事内では、それぞれ四角で囲まれた<解決策>の部分です)。
これらは何も世界について考える壮大な時間のためだけに当てはまるルールではなく、日常レベルでの思考にもつながることだと思います。
バイアスを捨て、知識をアップデートしながら、物事をあるがままに捉えられるようになるということですね。
ちなみに著者は、公衆衛生学の教授でしたが、残念ながら2017年に逝去しています。
もし彼が新型コロナウィルスのパンデミックの期間に活躍していたら、もっと世界の混乱は違う方向に行っていた可能性もあるのではないでしょうか。
本書を読んで、公衆衛生学を勉強することに興味がわいたのですが、そのためにはまず医療関連の学部(医学部、保健学部、看護学部など)に行く必要があるとのことだったので、残念ながら見送ることになりました。
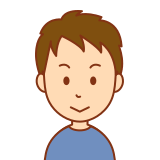
今から医学部目指すとか、人生何周やり直したらできるんだろ?
Thank you for reading!



コメント